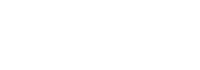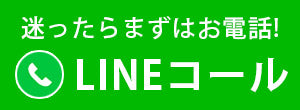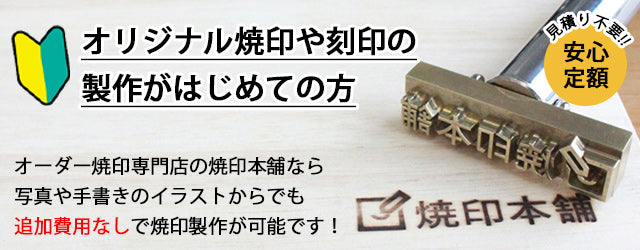今回は「革小物に自分のロゴを入れたいが、いろいろな革にどんな仕上がりになるか知りたい」「焼印をお願いするのも初めてなので、一番押しやすい方法も知りたい」というご相談をいただき、無料試し押しサービスで検証を行いました。
お預かりしたのは、厚みやシボ(表面のシワ模様)の有無、鞣し方の異なる複数の革小物用の革サンプル。同じデザインでも、革の種類によって焼き目や凹み方がどう変わるのかを比較するのが今回の検証ポイントです。
今回は以下の3つの加工方法で試し押しを実施しました。

1.打刻棒を使った手打ち刻印(非加熱の型押し)
2.電気式焼印(150W半田ごて+パワーコントローラー)
3.直火式焼印(ガスバーナー加熱+直火用持ち手棒)
仕上がりの違いだけでなく、「どの道具が一番扱いやすいか」という視点でもまとめています。
革・レザーへの焼印や刻印加工のポイント
革への加工において最も重要なのは、素材の特性を理解することです。今回の試し押しでは、厚みの違いやシボの有無、色など、様々な表情を持つ革に加工をしています。
特に革素材は、熱の伝わり方や圧力に対する反応が均一ではないため、加工の安定性を高めるための工夫が必要です。
同じ「本革」でも、タンニン鞣し・クロム鞣しなど鞣しの違いによって、焼き目の出方や熱による縮み具合が変わる点にも注意が必要です。

道具によって得意・不得意がある
打刻棒:非加熱のため、革へのダメージは少ないものの、素材のコシや厚みに仕上がりが大きく左右されます。
電気式焼印(半田ごて):コンセントがあれば使える手軽さが魅力。ただし温度管理が難しく、高温になりすぎると焼きつぶれや革の縮みが出やすくなります。
直火式焼印:立ち上がりが早くパワフルですが、温度調整がさらに難しく、焼きつぶれのリスクは最も高い方法です。
ロゴを「凹み(刻印)」で表現したい場合は、打刻加工か、温度調整ができる電気式焼印・ホットスタンプがおすすめ、というのが今回のポイントです。
3つの加工方法で革へのロゴ入れ検証
ここからは、実際に試した3つの加工方法について、使用機材、加工結果、そしてプロとしてのポイントを詳しく解説します。
加工方法①:打刻棒による手打ち刻印
ハンマーや金づちを使い、打刻棒を手打ちすることで刻印(凹み)をつける方法です。今回の試し押しでは、すべての革サンプルにこの方法で刻印を入れて比較しました。
使用機材: 打刻棒+ハンマー
加工温度: 非加熱(常温)
加工結果

厚みがあり、シボの少ない革では、人物イラストの輪郭や髪のラインまでしっかりと凹みが入り、ナチュラルな刻印表現ができました。

一方、薄手で柔らかい革や、表面に強いシボ加工がされている革では、凹みが浅くなりロゴがやや見えにくい仕上がりになっています。
加工のポイント

・非加熱のため、革が焦げる心配がなく、素材の色をそのまま活かした表現が可能です。
・均一な刻印を得るには、ハンマーで均等に、かつしっかりと打つ技術が必要です。特にシボのある革では、凹凸を埋めるようにしっかりと圧力をかけることが重要になります。
加工方法②:電気式焼印(半田ごて)
半田ごてを使って真鍮製の焼印を加熱して焼き付ける、もっともポピュラーな焼印方法です。今回はパワーコントローラーを併用し、おおまかに温度を落とした状態で革サンプルに試し押しを行いました。
使用機材: 150W電気ゴテ+真鍮製焼印+パワーコントローラー
加工温度: パワーコントローラーで出力を調整しながら加工
加工結果

タンニン鞣し系の革では、人物イラストの輪郭に沿って焼き目が入り、革色とのコントラストでロゴがはっきりと読める仕上がりになりました。特に厚みのあるブラウンの革では、焼き目とわずかな凹みが合わさり、存在感のあるロゴに仕上がっています。

一方で、デザインの線と線の間隔が狭い部分では、熱が回りすぎて線がつながり「焼きつぶれ」が発生している箇所も確認できました。また、高温のため、革の種類によっては熱ダメージで全体が縮んだり、波打ったような変形が出たサンプルもあります。

さらに、革の鞣し方によっては、高温で焼印してもほとんど焼き目がつかず、凹みだけがうっすら残るものもありました。クロム鞣しの革に多く見られる傾向です。
加工のポイント
電気式焼印は「コンセントがあればどこでも使える」という手軽さが魅力ですが、温度の上がり方が速く、放置するとすぐに高温になってしまいます。
・電気ごては手軽に始められますが、温度調整ができないため、革の種類や厚みに合わせた微調整が難しいのが課題です。
・特にデリケートな革や薄い革への加工では、短時間でサッと押すなど、経験とコツが必要になります。
加工方法③:直火式焼印
ガスバーナーなどの直接の火で焼印を温め、そのまま素材に押し当てるのが直火式焼印です。立ち上がりが早く、電源が不要なためアウトドア系の現場などでも人気のスタイルですが、今回の試し押しでも「温度調整の難しさ」がはっきりと結果に現れました。
使用機材: 直火用持ち手棒(ストレート型)+真鍮製焼印+ガスバーナー
加工温度: バーナーで十分に加熱した高温状態
加工結果

程よい温度帯をつかめたサンプルでは、焼き目がくっきりと入り、革の色とのコントラストも良好でした。ただし電気式焼印に比べると、温度の上下が激しく、少し熱を入れすぎるだけでデザインの細部が真っ黒に焼きつぶれてしまうケースが多く見られます。

特に顔の輪郭や目元など線が密集した部分では、線と線の間が完全に埋まり、もとのイラストが判別しづらくなるほど焼きが回っているサンプルもありました。革全体への熱ダメージも大きく、周囲の色が濃く変色しているものもあります。
加工のポイント

・直火式は温度調整が一切できないため、安定した仕上がりを得るのが最も難しい方法です。
・均一な仕上がりを目指すには、加熱時間や押し当てる時間の感覚を掴むための練習が不可欠です。
・革へのダメージを最小限に抑えつつ、しっかりと印影を出すには、革の厚みや種類を見極める熟練度が必要となります。
慣れれば強力な道具ですが、初めての方がいきなり本番の革小物に押すには、ややハードルが高い方法と言えます。
まとめ

今回の試し押しからわかったポイントを整理すると、次のようになります。
刻印(凹み)をメインにしたい場合
→ 打刻棒による手打ち刻印、もしくは温度調整ができる電気式焼印が向いています。厚みがありシボの少ない革ほど、凹みがくっきり出ます。
焼き目でコントラストを出したい場合
→ 電気式焼印・直火式焼印のどちらでも可能ですが、細かい線の多いデザインは焼きつぶれに注意が必要です。革の鞣し方によっては、そもそも焼き目がほとんどつかない場合もあります。
安定した量産を考えている場合
→ 温度調整機能を備えた「ホットスタンプTW350」のような機材を導入することで、革の種類や加工内容に応じて温度を変えながら、均一な仕上がりを再現しやすくなります。
今回の検証で明らかになったように、革は一つとして同じものがありません。特に初めて加工に挑戦される方は、ご自身の素材がどの加工方法に適しているか、試してみないと分からないことが多いのが実情です。
まずは無料試し押しサービスをご活用ください!
お客様の素材とご要望に最適な加工方法をご提案するため、無料試し押しサービスをご提供しています。
「自分の素材に焼印はできる?」「どの機材を選べばいい?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。プロの視点から、お客様の課題解決に寄り添い、最適な道具とノウハウをご提供いたします。